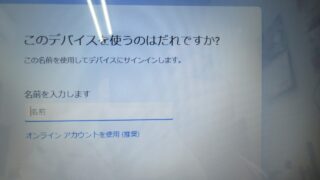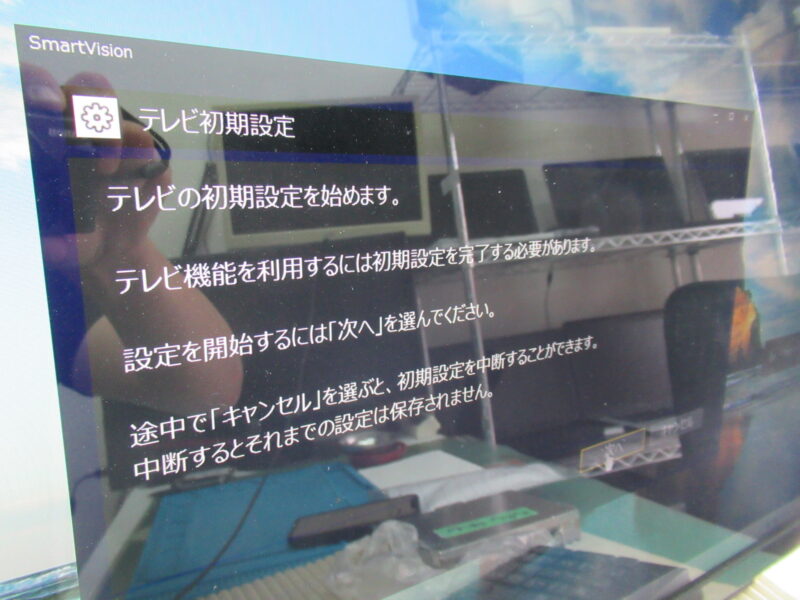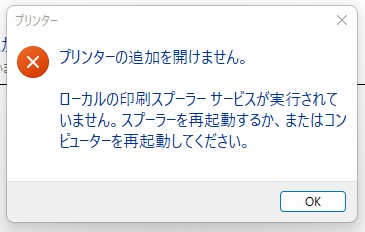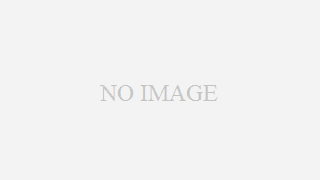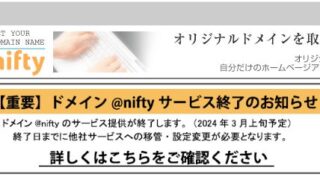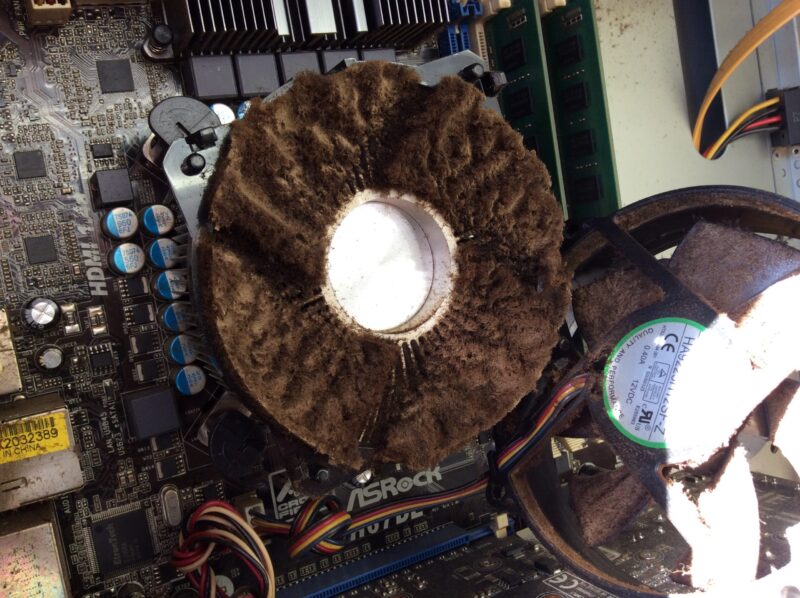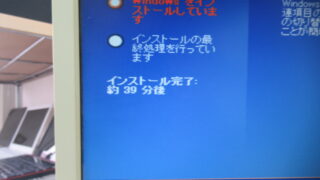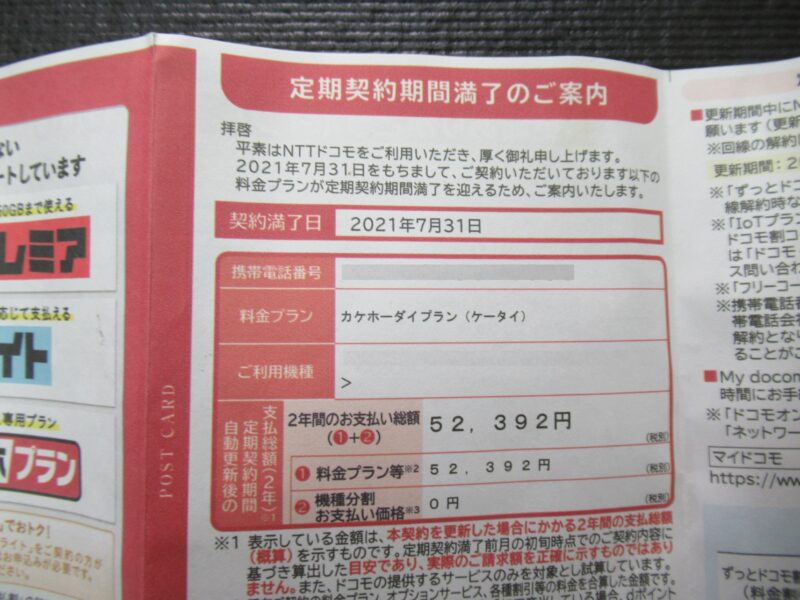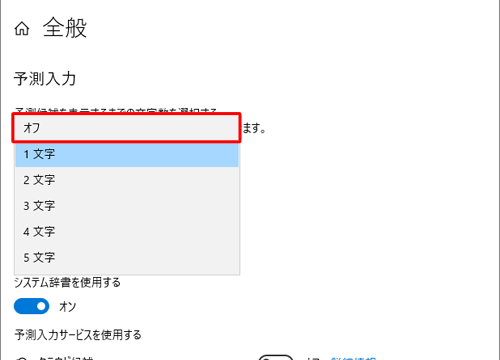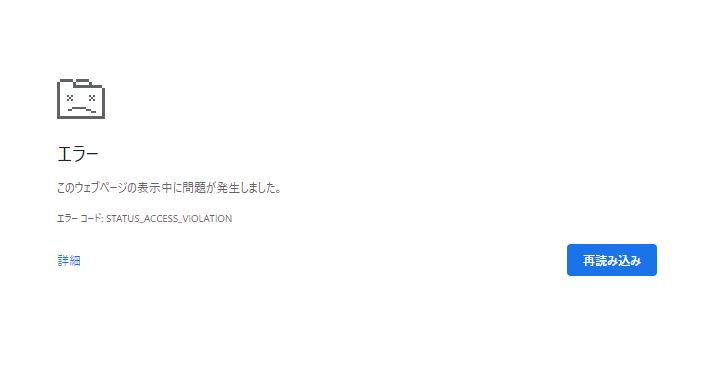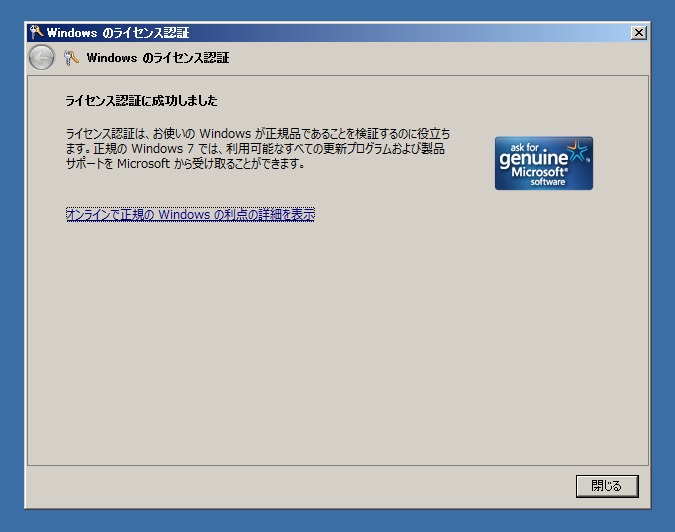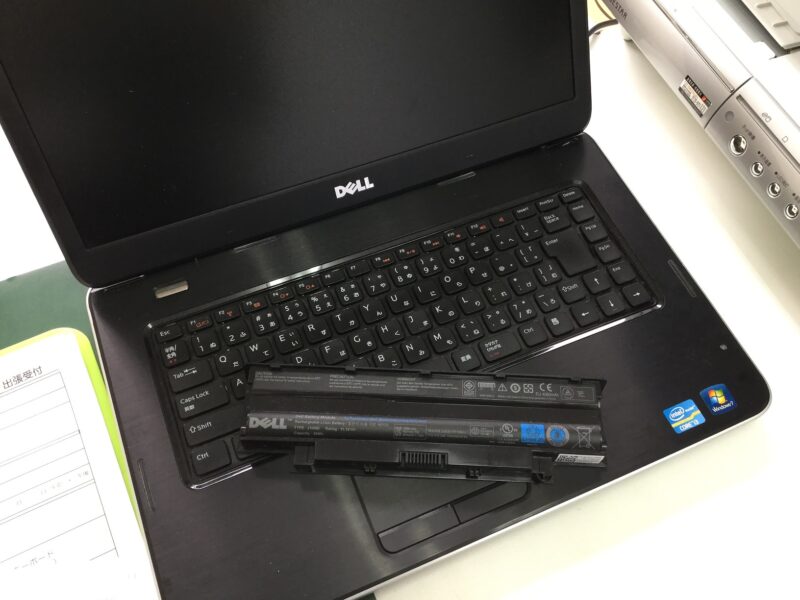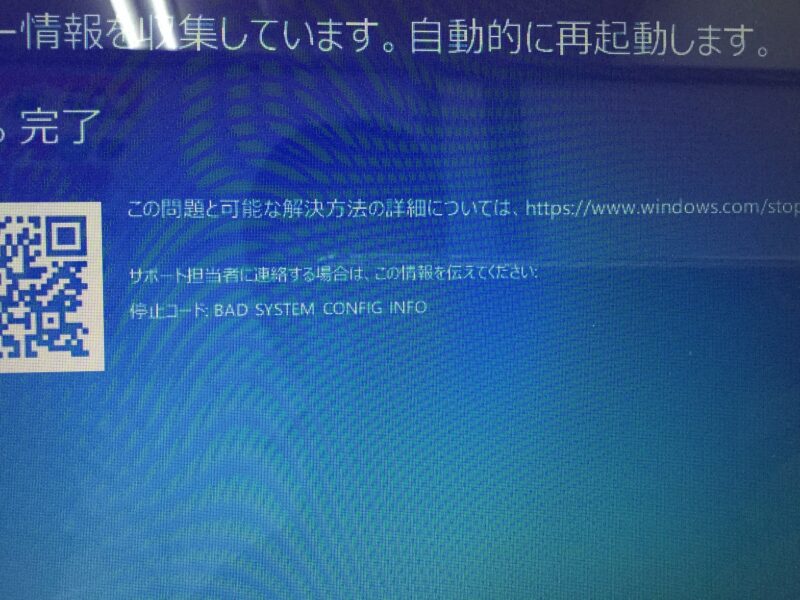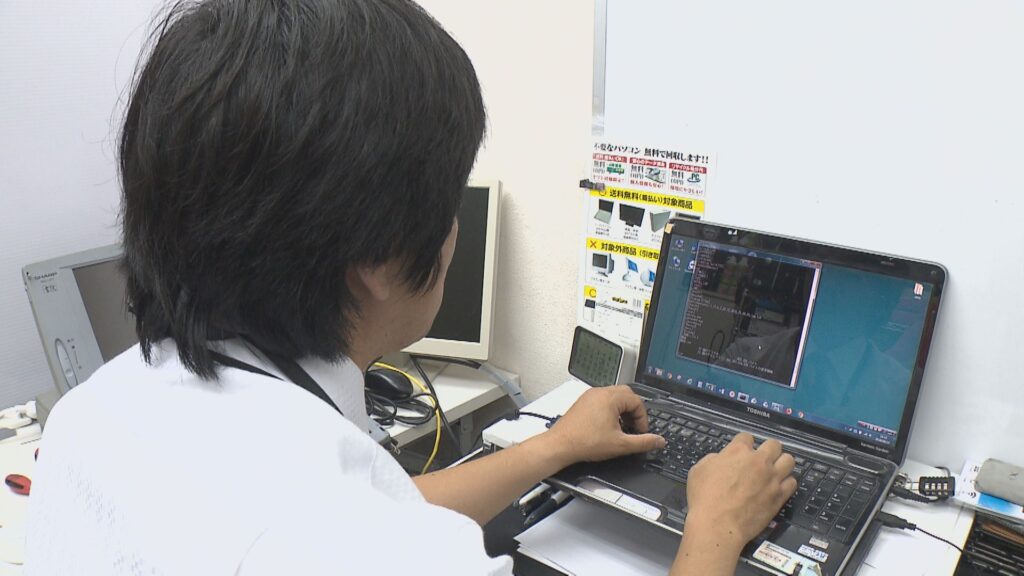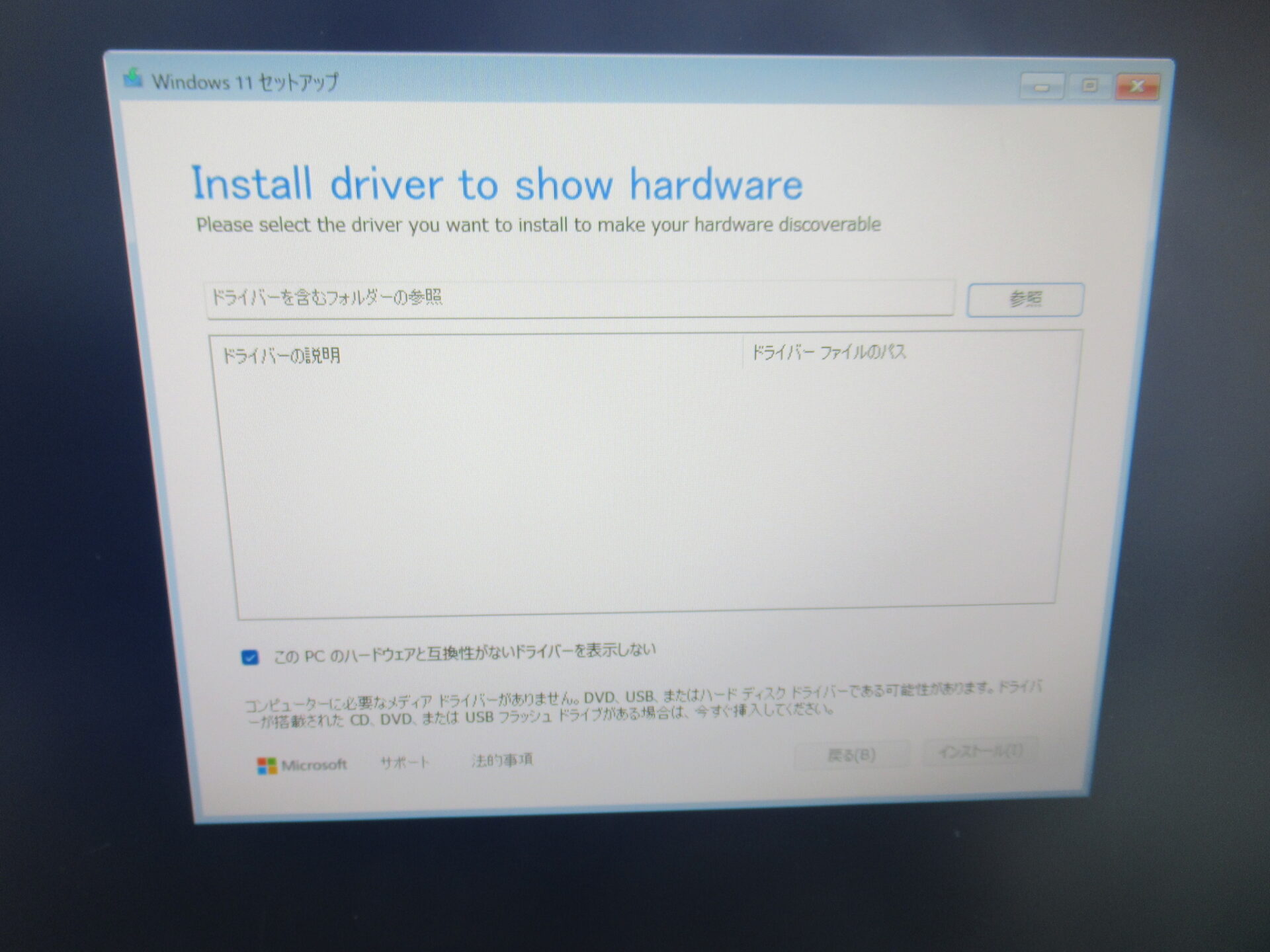(1) NECのPC事業
- 2011年:LenovoとNECが合弁会社「NEC Lenovo Japan Group」を設立。
- Lenovoが 51% の株式を持ち、実質的に経営権を握る形。
- NECブランド(LAVIE)を継続。
- 2016年:Lenovoが 完全子会社化 し、NECのPC事業を完全に吸収。
(2) 富士通のPC事業
- 2017年:Lenovoが 富士通のPC事業(FMV)を買収。
- 富士通のPC部門が「富士通クライアントコンピューティング(FCCL)」として分社化。
- Lenovoが 51% の株式を取得し、経営権を握る。
(3) 東芝のPC事業
- 2018年:Lenovoが 東芝のPC事業(dynabook)を買収。
- まず 80.1% の株式を取得し、2020年に 100%買収 して完全子会社化。
- 「dynabook」ブランドは継続。
2. BPRは強行されたのか?
Lenovoは ゼロベースでのBPRを強行したわけではないが、徐々に統合を進めた 形と考えられます。以下の点がその根拠になります。
(1) 日本市場を意識し、ブランドと事業体は維持
- NECのLAVIE、富士通のFMV、東芝のdynabookは ブランドを残したまま Lenovo傘下に移行。
- 完全にLenovoブランドへ統合するのではなく、日本市場での信頼を維持する戦略を採用。
- これは 日本市場が「国産ブランド」に対する信頼が強いため、急激な変革を避けた 可能性が高い。
(2) 製造拠点や開発拠点は維持(部分的に統合)
- NEC、富士通、東芝の 日本国内の開発・製造拠点 は一定程度維持された。
- ただし、Lenovoのグローバル生産体制(中国・台湾のODM)との統合が進んだ。
- 例:NECや富士通の一部モデルは 中国や台湾のODMメーカー(Compalなど)で生産 されるようになった。
(3) 経営・財務面の統合
- Lenovoは買収後、NECや富士通のPC事業の財務・経営管理をグローバル基準に統一。
- 特にコスト管理・調達の効率化を推進。
- 富士通やNECのPC事業は Lenovoとの統合でコスト競争力を向上 した。
(4) 人員整理や業務プロセスの見直し
- 急激な人員削減や強硬なBPRは実施されなかったが、経営効率化の一環として一部の業務プロセスが見直された可能性が高い。
- たとえば、Lenovo本社のグローバル基準に合わせて購買・生産・物流のプロセスが再設計された。
3. まとめ
LenovoはNEC、富士通、東芝のPC事業を買収したが、強硬なBPRはせず、徐々に統合を進めた。
🔹 急激な変革は避け、日本市場向けにブランドと事業体を維持。
🔹 生産・調達・コスト管理のプロセスはLenovo流に最適化。
🔹 開発拠点や一部の日本国内生産は維持し、信頼性を確保。
🔹 BPRというより、ソフトランディング型の経営統合を実施。
結論として、Lenovoは「徐々に最適化する」形でBPRを進めたが、日本市場の特性を考慮し、強行的な業務プロセス再設計は避けたと考えられます。